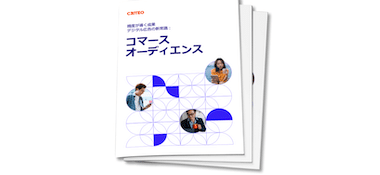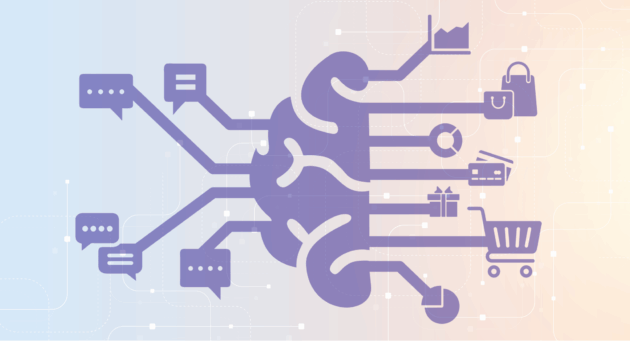5月5日は子どもの日。「子ども・子育て支援法」の定義では、「子ども=18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」とされています。今の子どもたちは、もちろん全員がいわゆる「デジタルネイティブ」。生まれたときからデジタル機器やインターネットがある環境で育ってきた世代です。ほんの10年ほど前は「小学生にスマホを持たせるか?」なんて議論も聞かれましたが、今ではもはやそんなことは話題にも上がらないほど、子どものインターネット利用が当たり前になってきている感があります。
では、日本の子どもたちは具体的に、どんな風にインターネットを使っているのでしょうか?こども家庭庁が行った「令和5年度青少年のインターネット利用環境実態調査」の結果から、その傾向を探ってみました。
低年齢層の子ども、インターネットは「テレビで」が多数
低年齢層(0歳から9歳)の子どものインターネット利用状況について調べたところ、全体の74.9%の子どもたちが日常的にインターネットを利用していることがわかりました。利用率を年齢別に見てみると2歳児が約60%、6歳児で約80%と年齢が上がるにつれて利用率が高くなり、12歳以上になると99%がインターネットを利用しています。12歳はまだしも、2歳がインターネットを利用している光景というのは、実際に子どもが身近にいる人以外には想像しがたいものかもしれません。ただ、この年齢の子どもたちが利用している「インターネット」は、大人のように物を調べたり発信したり、買い物をしたりするためのものではありません。低年齢層の子どもたちの利用内容の内訳をみると、「動画を見る」が圧倒的に多くて93.6%、「ゲームをする」が64.7%、「勉強をする」が40%でした。そう、多くの子どもたちにとってインターネットはYouTubeやTikTokで動画を見るためのもの。家事や仕事で子どもの相手ができない間や、飛行機など長時間の移動で子どもが退屈してしまいそうなとき、動画を見せることで救われた・・・・・というパパ・ママも多いのではないでしょうか。今や、インターネットは子育ての必須アイテムと言っても過言ではないのかもしれません!
動画の視聴がメインなので、子どもたちがインターネットを利用するために使っている機器は「テレビ」が最も多く、53.3%。次いで「自宅のPCやタブレット」が38.0%、「ゲーム機」が35.8%、「スマートフォン」は27.1%でした。低年齢層の子どもたちの多くはテレビや家族のPC・タブレット、つまり家族と共用の機器を使って、家族の目の届く範囲で動画の視聴を楽しんでいるようです。しかし、年齢が上がってくると状況は一変。10歳~17歳の青少年層に同じ質問をしたところ、インターネットを利用するために使っている機器で最も多かったのが「スマートフォン」で74.3%に。専用のスマートフォンを持っている割合も15.9%(低年齢層)⇒91.9%(青少年層)に急上昇しています。同調査によると、利用するデジタル機器の共用⇒専用の割合が逆転するのは、10歳。10歳では専用の機器を持つ子どもが65%を超えています。
小学生の平日のネット利用時間は3時間36分に!
このように、もはやほとんどの子どもたちにとって当たり前の存在になっているインターネットですが、保護者として気になるのはやはり、その利用時間。何時間もゲームや動画視聴に没頭して全然勉強や手伝いをしない子どもにイラっとさせられたり、「依存気味では・・・」と心配している方も多いことでしょう。今回の調査で平日1日あたりのインターネットの利用時間を聞いたところ、年齢とともに利用時間は上昇傾向にあり、低年齢層(0歳~9歳)は2時間5分、小学生(10歳以上)で3時間46分、中学生は4時間42分、高校生は6時間14分にも上りました!中学生は1日の6分の1を、高校生は4分の1をオンラインで過ごしているということになりますね。この数字を見ると、今の子どもたちの生活が、その保護者が同じ年齢だったころの生活とは全く違うものになっていることがよくわかります。
ちなみに、インターネットを使って何をしているのか、利用目的別の時間を聞いたところ、最も多かったのが「趣味・娯楽」で約2時間57分でした。インターネットを使って学習をしている子どもも多いものの、その利用時間の平均は「1日あたり1時間未満」が52%で最多に。オンラインでの学習時間は、残念ながら保護者が期待するほど多くはないようです。
子どもは意識していない?「ネット利用のルール」
ここまで多くの時間を子どもがネット上で過ごしていると聞くと、心配になるのが生活・学業への影響やネットトラブル被害です。「オンラインゲームばかりしていて成績が低下」、「いかがわしいサイトにアクセスしていた」、「勝手にゲームで高額課金をしていた」といったケースも珍しくありません。そんなトラブルを避けるために多くの保護者が、家庭内でのネット利用に関するルールを設けています。今回の調査でも低年齢層の家庭の約80%、青少年層の家庭の約65%が独自の家庭ルールを設けていることがわかりました。しかし、ルールを設けている家庭の割合は年齢が上がるとともに減少し、小学生ではルールを決めていると答えた保護者が約90%だったのに対し、高校生では58.5%に減少。しかも、58.5%の保護者が「ルールを決めている」と回答しているのに、肝心の子ども(高校生)で「ルールを決めている」と回答したのは41.9%。つまり、親だけが「うちはルールを決めている」と思っていて、子どもは気づいていない・・・というケースも珍しくないことがわかりました。ルールを決める際には、親子で同じ認識が持てるように情報共有を徹底したいですね。
なお、スマートフォンを利用している子どもに限定した調査では、「利用に際して何らかの管理をしている」と回答した保護者が全体の83.4%に。具体的な取り組みとしては、「フィルタリング」(44.2%)、「対象年齢にあったサービスやアプリを使わせている」(37.4%)、「利用しても良い時間や場所を決めて使わせている」(37%)が上位でした。しかし、上位2つについては高校生ともなると、指示に従わせるのはなかなか難しいもの。トラブルを避けるためには、他の生活習慣と同じように、幼少期から時間をかけてインターネットとの向き合い方や利用のルールをしっかり教え、習慣として身に付けさせるのが大切です。子ども時代のインターネット利用スタイルは、大人になってからの余暇の過ごし方や買い物の仕方、ライフスタイルにも大きな影響を及ぼすもの。インターネットの良い面だけでなく悪い面もしっかり説明して、家族みんなの問題として一緒に取り組んでいきたいですね。子どもには利用時間を制限して、大人は自由に使いたい放題・・・では、まったく説得力がないはずですから!